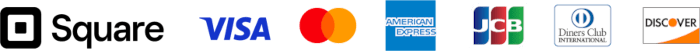不倫慰謝料請求裁判や訴えられたときの分かりやすい法律相談
不倫の慰謝料を請求されると、話がこじれて裁判を起こされてしまうケースが少なくありません。
多くの方にとって裁判(訴訟)は初めての経験で、混乱してしまう方も多いでしょう。
不倫の裁判を放置していると高額な慰謝料の支払い命令が出る可能性もあるので、訴えられたら,弁護士にも相談し,当初から適切に対応する必要があります。
今回は不倫慰謝料の裁判の流れや訴えられたときの対処方法を弁護士が解説しますので、不倫トラブルに巻き込まれた方はぜひ参考にしてみてください。
1.不倫の裁判とは
不倫の裁判とは、不倫の慰謝料を請求するための裁判(訴訟)です。一般的には,不法行為に基づく損害賠償請求となります。
裁判には訴えた側と訴えられた側がいて、訴えた方を「原告」、訴えられた方を「被告」といいます。
不倫の裁判では不倫された配偶者が「原告」、不倫した(と主張されている)人が「被告」となります。
一般社会では「被告」というと刑事事件絡みの悪いイメージもありますが、民事では必ずしも責任があるとは限りません。単に「訴えられた」というだけで悪いことをしたわけではなく、被告が勝訴する案件も多々あります。
裁判所から届いた書類に「被告」と書いてあっても、あせらずに対応を進めましょう。
2.不倫裁判の流れ
不倫の裁判を起こされたらどのような流れで手続きが進んでいくのか、みていきます。
STEP1 訴状が送られてくる
裁判が始まると、まずは裁判所から訴状とよばれる書類が送られてきます。
訴状とは、原告が訴える内容を法律的にまとめた書類です。
訴状と一緒に「答弁書催告状」「第1回口頭弁論期日呼出状」などの書類も一緒に送られてくるのが一般的です。
また裁判所からの書類は「特別送達」という特殊な郵便で配達されます。手渡し式になっているので、不在で受け取れなかった場合などには無視せずに再配達などの方法で受け取りましょう。
STEP2 答弁書を提出する
裁判所から送られてくる書類には、訴状と一緒に「答弁書催告状」が入っています。答弁書とは、被告が原告に対する反論を明らかにするための書類です。
「答弁書催告状」には,例えば,名古屋地方裁判所民事第6部に係属した,とか,担当書記官の名前や連絡先が記載されています。不明点があるときは,問い合わせ先となりますので,「答弁書催告状」など裁判所書記官の氏名や事件番号が記載された書面は無くさないようにしましょう。
第1回期日までに答弁書も提出せず期日にも出頭しない場合、被告は原告の言い分を全部認めたことになってしまいます。そうなると高額な慰謝料の支払い命令が出る可能性が高いので、弁護士に相談のうえ,代理を依頼するか,必ず答弁書を作成して提出しましょう。
答弁書と一緒に被告側に有利になる証拠も提出できます。
この時点で,弁護士に相談することを検討しましょう。
本人訴訟の場合,答弁書や証拠については3部用意して2部を裁判所へ送る必要があります。1部は原告へ送られるので、原告にみられて良いことのみを記載すべきです。
1部は自分の控えにしましょう。
STEP3 第1回口頭弁論期日
裁判所から指定された日に第1回期日が開かれます。
事前に答弁書を提出している場合、第1回期日には出頭してもしなくても良い場合があります。これを擬制陳述といいますが,弁護士代理人が就いているケースにおいて擬制陳述が認められる場合が多いので,本人訴訟で,出頭しない場合、裁判所書記官によく連絡をしておくべきです。擬制陳述が認められると,答弁書を陳述した扱いになります。
自分で裁判官や原告代理人などに何か言いたい場合や和解の話を進めたい場合などには必ず出席しましょう。
なお弁護士に対応を依頼すればご本人が出席する必要はありません。
STEP4 争点や証拠の整理
第1回期日が終わると、その後は争点や証拠を整理する期日が何度か開かれるのが一般的です。弁論準備期日といって、お互いに書面や証拠を出し合い、どこが噛み合っていないのかを明らかにしていく手続きです。最近は,「書準」といって,双方電話による「書面による準備手続」の「進行協議期日」の中で,争点整理が行われていることが多くなっています。
弁論準備手続期日においては,法廷ではなくラウンドテーブルなどの通常の部屋で話し合いながら作業を進めます。
書面による準備手続は様々な形態があり,①双方電話による場合,②teamsを用いる場合,③進行協議期日を指定せず書面による準備のみを行い準備事項を書面で知らせてくる場合などが考えられます。
ただ調停ではないので、法律的に意味のある主張をしなければ、後に判決を受ける際に不利益が生じてしまいます。
弁護士に任せていれば、依頼者は出頭する必要はありません。対処方法に自信がない場合や忙しい場合には弁護士に裁判を依頼するのが良いでしょう。
STEP5 尋問
争点や証拠の整理が終わると、尋問が行われます。
不倫慰謝料請求の場合には、不倫相手である被告や不倫した配偶者の尋問が行われるケースが多数です。
不倫した配偶者(不倫相手)と連絡をとれるようであれば、事前に連絡を取り合って尋問の準備をしましょう。
なお不倫相手が原告側についている場合、無理に協力させるのは困難です。その場合でも弁護士と打ち合わせてどのような対応をとるべきか、尋問の予行演習を含めて綿密に打ち合わせをする必要があります。
STEP6 結審
争点や証拠の整理、尋問が終わったら裁判が結審します。
結審後、1ヶ月程度で判決言い渡し期日が指定されます。
STEP7 判決言渡し
指定された期日に判決が言い渡されます。
判決言渡し期日には出頭する必要はなく、数日後、裁判所から特別送達で判決書が送られてきます。
弁護士に依頼した場合には弁護士が判決書を取得して連絡してくれるので、待ちましょう。
STEP8 控訴
判決を受け取ってから2週間が経過するまでの間は控訴ができます。
控訴とは、民事裁判における不服の申立手続きです。
判決内容に納得できない場合には控訴を検討しましょう。
たとえば以下のような場合、控訴する方が多数です。
- 不倫していないのに不倫したと認定された
- 慰謝料が高額過ぎる
裁判を弁護士に依頼した場合、弁護士が控訴に見込みがあるかどうかの意見を伝えてくれるのが一般的です。法律家の意見をよく聞いた上で控訴するかどうかを決定しましょう。
3.不倫裁判を放置するリスク
不倫の裁判を起こされたとき、放置してはなりません。
無視していると以下のようなリスクが発生します。
3-1.相手の言い分を認めたことになる
裁判では、被告が答弁書を提出せず期日にも出頭しない場合、原告の言い分をすべて認めた扱いをされてしまいます。
本当は不倫していないのに不倫したと認定されたり、事実以上に悪質な不倫と認定されて高額な慰謝料の支払い命令が出たりするリスクが高まります。
時効が成立している場合や相手方夫婦の関係が初めから破綻している場合には慰謝料を払わなくて良い可能性もあるのに、そういった主張もできません。
相手の言い分を認めたくない場合には、必ず答弁書を提出しましょう。また,一度,弁護士に相談するようにしましょう。
3-2.高額な慰謝料の支払い命令が出る
裁判を無視していると、原告の言い分がすべて認められてしまいます。
裁判所は原告の主張を一方的に聞いて判決を書くので、どうしても不倫慰謝料は高額になります。
きちんと争った場合よりも慰謝料が高くなるリスクが高まると考えましょう。
なるべく慰謝料を低額に抑えたいなら必ず裁判に対応すべきです。
3-3.遅延損害金や弁護士費用が加算される
不倫の裁判を放置すると、判決で慰謝料の支払い命令が出るのが通常です。
そうなったら、遅延損害金や弁護士費用が加算される可能性が濃厚となります。
遅延損害金とは、慰謝料の支払いが遅れたことに対する損害賠償金です。現時点では年率3%として計算されるので、不倫があった時期から日が経っていると高額になる可能性があります。
相手が弁護士をつけている場合には、慰謝料の認容額(支払い命令が出た額)の10%が弁護士費用として加算されるのが一般的です。
これら以外に探偵調査にかかった費用の一部が加算されるケースもあります。
なるべく支払いを減らしたいなら、必ず応訴して諸費用が加算されないように対応すべきです。
3-4.差し押さえのリスクが高まる
裁判を起こされたときに放置すると、いずれは判決が出ます。
判決が確定すると、原告はいつでも被告の財産を差し押さえられる状態になります。
たとえば以下のような財産が差し押さえ対象です。
- 預金
- 保険
- 車
- 不動産
- 給料
- 敷金返還請求権
給料を差し押さえられたら、毎月やボーナス時の手取り額が減ってしまうので、生活にも支障が及ぶでしょう。
差し押さえを受けないよう、裁判をされたら適切に対応を進めるべきです。
4.答弁書の期日を過ぎた場合の対処方法
答弁書には「提出期限」が定められています。
よく「提出期限を過ぎたらどうすればよいですか?」というご質問を受けるので、お答えします。
結論からいうと答弁書は、提出期限を過ぎても必ず提出すべきです。
期日までに間に合えば、相手の言い分を認めた扱いにはなりません。
無視するのが一番悪いので、そのようなことをせずに早めに弁護士へ相談しましょう。
期日の1日前などであっても弁護士に相談すればなんとかなるものです。
あきらめずに不倫トラブルに詳しい弁護士の力を頼ってください。
5.裁判上の和解で話し合って解決できることも
不倫の裁判を起こされたとき、必ずしも判決になるとは限りません。裁判上の和解で解決できるケースも多々あります。
裁判上の和解とは、裁判官の仲介によって判決をせずに話し合いでトラブルを終わらせる手続きです。
不倫慰謝料の裁判が和解になると、以下のようなメリットがあります。
- 遅延損害金が加算されない
- 弁護士費用が加算されない
- 分割払いが可能となる
- 差し押さえリスクが軽減される(約束とおりに支払えば差し押さえを受けない)
弁護士に裁判を任せると事案の進行状況に応じて上手に和解できる可能性が高くなるので、早めの段階で依頼しましょう。
6.不倫の裁判で訴えられたときの対処方法
不倫の裁判で訴えられたら、以下のように対応すべきです。
6-1.答弁書や証拠を提出する
まずは答弁書や証拠を揃えて、できるだけ提出期限までに裁判所へ提出しましょう。
無視するのが一番良くない対応です。郵便を受け取らずに放置するのもNGです。
自分で答弁書を作成できない方は、早めに裁判所から届いた書類をもって弁護士へ相談に行きましょう。
6-2.期日に出頭する
弁護士に依頼しないなら、必ず第1回期日には出頭するようおすすめします。
当日、和解の話が進む可能性もあります。
6-3.弁護士に依頼する
裁判を素人の方が単独で進めるのは困難です。裁判の場合,弁護士代理人が就くケースが多いのも事実です。
弁護士に依頼すればほとんどの期日において、当事者が出席する必要すらありません。出頭が必要なのは,尋問期日くらいといえるかもしれません。
訴訟を追行することは,差し押さえなどの不利益も防止できる可能性が高まります。
訴状が届いたら、なるべく早めに弁護士へ相談しましょう。
名古屋駅ヒラソル法律事務所では男女問題,不倫慰謝料トラブルの解決に力を入れています。お困りの方がおられましたらお気軽にご相談ください。